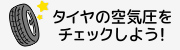ダンロップヒストリー

ダンロップの歴史
- 1888
- 1889
- 1905
- 1909
- 1913
- 1920
- 1930
- 1947
- 1954
- 1956
- 1960
- 1972
- 1986
- 1988
- 1991
- 1998
- 現代
- 2001
- 2002
- 2005
- 2006
- 2008
- 2013
- 2014
-
1888

空気入りタイヤの誕生・成長、そして未来。
タイヤの歴史はダンロップと共にある。
いま、自動車やバイク、自転車のタイヤといえば、誰だって空気入りタイヤを思い浮かべるだろう。地球上いたるところにある空気のすぐれた弾力性を利用し、ソフトな乗り心地が得られるばかりか、抵抗が少なく、グリップがよく、騒音が低い。空気入りタイヤにまさるタイヤは、永久にあらわれそうにないとも思えるほどだ。空気入りタイヤが発明されたのは、意外に新しい。それでも、話は120年以上前にさかのぼる。
-

J.B.ダンロップの息子ジョニー

アイルランドのベルファストで、獣医として豊かな生活を送っていたJ.B.ダンロップは、10歳になった息子のジョニーから「ボクの3輪自転車をもっとラクに、もっと速く走れるようにして」と頼まれた。発明心の旺盛なダンロップはゴムのチューブと、ゴムを塗ったキャンバスで空気入りタイヤを作り、これを木の円盤のまわりに鋲で固定した。これに乗ったジョニーの評価は上々であった。しかも、かなり悪い道を走っていたのにタイヤは全く無傷だった。
スタートはJ.B.ダンロップが息子のために作った自転車のタイヤだった。そしてこの年、J.B.ダンロップの特許が発表された。 -

J.B.ダンロップが最初に作った空気入りタイヤとその実験風景(いずれも当時を復元したもの)。

-

空気入りタイヤ装着した自転車を持つJ.B.ダンロップ

-

1888年、J.B.ダンロップに与えられた空気入りタイヤに関する特許状

-
1889

J.B.ダンロップの「マミータイヤ」(ロンドンの科学博物館蔵)

J.B.ダンロップが自転車メーカーに作らせたキャンバスをスポークの間に通して、リムと一体にチューブの上に巻く方法で固定した、空気入りタイヤ「マミータイヤ」を着けて自転車レースに出場したW・ヒュームがソリッド・タイヤを使った強豪選手を寄せつけず圧勝した。このニュースはたちまちのうちに広がり、さらにダンロップの特許が発表されると世間の関心はますます高まった。1889年11月、ダブリンに「The Pneumatic Tyre and Booth’s Cycle Agency, Ltd.」が設立され、ダンロップは特許権を譲渡して、役員の一人になった。現在、ダブリンのこの地に「1889年、世界初の空気入りタイヤ工場が1888年12月7日J.B.ダンロップに与えられた特許に基づいて、この地で生産を開始した」と書きしるされたブロンズの銘板がある。1892年にコベントリーに移り「Dunlop Pneumatic Tyre Co.」となり、更に1900年バーミンガムに移って「Dunlop Rubber Company Ltd」となる。
-

自転車レースで先頭を行くW.ヒューム選手のレース風景イラスト

-

ワイヤドオン方式(上)
クリンチャー方式(下)
創業間もない「The Pneumatic Tyre and Booth’s Cycle Agency, Ltd.」は、これらの特許を買い取った。いずれも会社の発展に貢献。
ワイヤドオン方式が、現在の乗用車用のタイヤとリムの組み合せの原型である。 -
1905

ケーシング材料として、1890年代から採用された、たて糸だけのコードファブリック

当時、自動車のタイヤにはトレッドパターンがないので、少しスピードを出すと真っ直ぐには車を止められないほどであった。また、タイヤは頻繁にパンクした。そこで、チェーンを巻いたり、革やスチールのボタンをつけたレザーバンドをタイヤにかぶせるようなことが実際に行われた。ダンロップ社が初めてタイヤトレッドに簡単な横溝のパターンをつけたのは、この年のことである。これは未加硫トレッドの上の何カ所かに短い鉄棒をおいてからラッピングし、加硫の熱で刻印するという方法で作られてた。この記念すべきタイヤのトレッドの表面には、ラッピングキャンバスの細かい布目が見られる。
-

1905年、ダンロップ社は、初めてトレッドに横溝のパターンをつけた自動車用タイヤを開発

-

ウェルベースリム
クリンチャーリム
-
1909

日本初の近代的なゴム工場が操業を開始

1909年10月、英国ダンロップ社は外人居留地の神戸市浪花町に「The Dunlop Rubber Co.(Far East),Ltd.」の日本支店を設け、同脇浜に工場を建設して操業を開始しました。日本初の近代的なゴム工場の創業です。工場の建設や操業の指導を行ったのは、後に代表取締役となるV.B.ウイルソンで、技師と3人の職長とともに来日しています。先進のゴム会社であるダンロップをバックとするだけに、日本支店は技術力と販売力ともに強力で、後に日本のゴム工業の指導的な役割を果たすようになりました。ちなみに、日本支店は1917年に日本法人となり、「ダンロップ護謨(極東)株式会社」として登記されました。
-

操業当初は自転車用タイヤと人力車用タイヤを製造

英国ダンロップ社の日本支店の工場では、当初自転車用タイヤと人力車用タイヤが製造されました。自転車は日露戦争後に急速に普及しましたが、そのタイヤは大部分が輸入に頼っており、自転車用タイヤの国産化が市場から切望されていたのです。一方、人力車用タイヤはそれまで鉄輪のままで走っていたものが、ゴムのソリッドタイヤに切り替わるという革新的な出来事でした。
-
1913

国産の自動車用タイヤ第1号が誕生

英国ダンロップ社の日本支店は1913年に自動車用タイヤの生産を開始します。国産の自動車用タイヤ第1号の誕生です。当時の日本の自動車普及率はまだまだ低く、1912年の時点で全国の自動車保有台数はわずか521台に過ぎませんでした。しかし今後自動車保有台数は大きく伸びる、またインドネシアやシンガポールなどにも輸出できるという見通しに基づいた決断でした。当時の自動車用タイヤの日産は25~26本で、製法はファブリックタイヤまたはキャンバスタイヤと称した、ゴム引きした綿布を重ね合わせるやり方を採用していました。製造開始から間もなくして、日本での自動車の普及が急伸。1926年には保有台数が4万70台にまで増え、それに伴って同社は日本における自動車用タイヤ製造のリーダー的存在に成長しました。
-
1920年代

第1次世界大戦の頃のソリッドタイヤをつけた大型車輌

1920年代から30年代にかけては、タイヤの技術が花を開き、また将来に向けて深く根を下ろしていった時代であった。1922年のモーターショーでは、ダンロップ社はディタッチャブルフランジのリムをつけたワイドタイヤを出し。1924年には、今後はワイドタイヤを標準にすると発表し、また乗用車タイヤ用にウェルベースリムの改良を推進した。レーシングドライバーのP.デュトワがダンロップの依頼でワイドタイヤと新しいウエルベースリムの組み合わせをテストし、空気が抜けたときでも、タイヤはこの新しリムからはずれにくいことを示したのはこのときである。このリムの開発には、丈夫で軽く、扱いやすいということだけでなく、他にひとつの大きな要求があった。それは、これまでよりタイヤの空気圧を下げて乗り心地をよくすることである。これらの要求はリムのプロファイルを変えることで達成する事ができた。
-

1924年レーシングドライバーP.ドュトワがダンロップのワイヤドタイプタイヤウェルベースリムの組合せテスト

20世紀の初め6.3~7.0kg/cm2もあった空気圧は、1920年代に入って4.2~4.9 kg/cm2まで下がっていったが新しいリムとタイヤの組合せによりさらに2.1~2.4 kg/cm2まで下がる。そして、1948年頃には1.7kg/cm2までになった。タイヤの負荷能力を保ちながらその内圧を下げるのには、タイヤの幅を広げる方向に進むことになる。1920年代初めのもうひとつの大きな進歩は、自動車タイヤにもようやく、キャンバスに変わってよこ糸のないコードが使われるようになったことである。タイヤコードの使用により、タイヤの平均寿命はこれまでの3倍以上になった。こうした飛躍的な性能の向上は、のちのラジアルタイヤによる性能改良と並び、タイヤの歴史の中で、最も大きな進歩であった。タイヤの技術開発の進め方も、この時代には大きく変わってくる。これまでは経験の蓄積と直感からの試行錯誤で進んできたが、それが科学的な取り組みに移行してゆく。
-

1900年に設置された技術研究室を母体として1920年、中央研究所発足

ダンロップ社では、研究所を中心に、新進の技術者たちがタイヤの生産過程で起こるいろいろな問題に取り組み、試験室でこれを評価、解析した。素練りゴムの可塑度、加硫ゴムの弾性と動的特性、ゴムの摩耗等の試験機を次々に開発し、これによって得られた試験結果と工場でのゴムの加工性、タイヤの発熱や摩耗等の関係を研究した。数学モデルを使ってバネ下振動を論じ、タイヤを懸架システムのひとつとして捉えていこうとする考え方も、1920年代の中頃、ダンロップ社の研究所から生まれた。1927年、サンビームのツインエンジンを積んだ特別カーに着けられた高速タイヤが、アメリカ・フロリダ州のデイトナビーチで世界で初めて時速200マイル(320㎞)のカベを破る世界記録に挑んだ。そして、この車を操縦する、H.D.O.ゼグレブ少佐は、平均時速203マイル(326.6㎞)の新記録を見事に達成した。これはタイヤの高性能を室内走行試験機で評価できることを示した貴重な経験であった。
-
ダンロップ装着チームがル・マンで初優勝
1924年開催の第2回ル・マン24時間レースにおいて、ダンロップのタイヤを装着したベントレー・3リットルは、強力なライバル車を押し退けて見事に優勝を飾ります。ダンロップにとって、ル・マンでの初優勝でした。その後、ダンロップは同レースで連戦連勝し、1931年大会までに8連覇を成し遂げます。また、ダンロップはブガッティともタッグを組み、第2次世界大戦で中断する直前の1939年大会ではダンロップのタイヤを履くブガッティ・タイプ57Cが優勝を果たしました。
-

ダンロップのスペシャルタイヤを装着して初めて時速200マイルを突破

1927年、ダンロップはスピード記録に挑戦するために製作されたサンビーム1000HPに、特別に開発したタイヤとホイールを供給します。足もとをダンロップスペシャルで武装した流線型アルミニウム製ボディのサンビーム1000HPは米国デイトナビーチのコースに持ち込まれ、ヘンリー・セグレブ(シーグレーブ)のドライブで時速203.79mph(327.9km/h)の新記録を打ち立てました。
-
1930

1930年、ダンロップタイヤによるトラクター用タイヤの実験

1930年代になるとタイヤのトレッドパターンについての研究が進んだ。パターンは、それまでにトレッドが均一に摩耗するように、横溝またはブロックタイプから縦溝タイプに変わっていたが、濡れた路面でのグリップをよくするために、リブの内側に凸凹をつけ、さらにリブの表面にナイフカットという細かい刻み目を入れるようになった。また道路舗装が滑らかになり、低騒音のサルーンカーが増えてからは、走行中のタイヤの出す音は耳障りになってきた。それはパターンの配列の規則性からくるものでこの配列を不規則にすれば、音の周波数にピークがあらわれにくくなるので、耳障りな音は小さくなる。1930年代にはじまったこのバリアブルピッチの考え方は、現在のタイヤ設計にも取りいれられている。さらに車の操作性能、タイヤのコーナーリング特性の研究が展開されてきたのもこの時代からである。
-
1947

スピード記録へのチャレンジにスペシャルタイヤを提供

第2次世界大戦後間もなくのダンロップは、スピード記録に挑戦する多くのチームにスペシャルタイヤを提供しました。そのなかで、ジョン・コッブが駆るRailton Mobile Specialが1947年に米国ユタ州で開催されたボンネビルで最高速度394.19mph(634.39km/h)の新記録を樹立。世界中のクルマ好きから喝采を浴びました。
-
1954

初期のチューブレスタイヤ構造図

空気入りタイヤに2つの大きな変化がやってきた。ひとつは、チューブレスタイヤの登場である。空気入りタイヤの悩みは、クギ等が刺さったとき、チューブに穴があいて瞬時に空気が抜けることであった。そこでチューブをなくし、タイヤの内側にやわらかいライニングをつけることが発明された。もうひとつの大きな変化はラジアルタイヤの登場である。このタイヤはケージングを形成するタイヤコードが、タイヤの周方向に直角になるように、すなわちラジアル方向に配列され、その上に周方向に近い角度をもったベルトを、たが状に巻いた構造である。ラジアルタイヤでは、このベルトの作用で、少しハンドルをきるだけで車は滑らかに旋回できるようになり、そのためにトレッドの摩耗は減り、特に乗用車用タイヤでは、その寿命は2倍にのびる。
-
1956
世界最高峰のレースであるF1グランプリに参戦
フォーミュラマシンの最高峰レースとなるF1は1950年より開始されます。当初の参戦はヨーロッパ大陸の自動車チームが中心で、英国メーカーはイギリスGPなどのスポット参戦に限られていました。しかし、1956年シーズンになるとヴァンウォールが準レギュラー格でエントリー。タッグを組んだのは、同じ英国のタイヤメーカーで、ル・マンなどのスポーツカーレースで高い実績を誇るダンロップでした。ダンロップの協力のもと、マシン開発とレース運営の技術を磨いていったヴァンウォールは、1958年シーズンになると圧倒的な速さを見せ、S.モスとT.ブルックスの2人のドライバーで全11戦中6勝を獲得。 この年から始まったコンストラクターズチャンピオンシップの初代王者となりました。F1の世界でも高性能が実証されたダンロップは、翌’59年シーズンからフェラーリなどにもタイヤを供給。結果として、1958年から1965年シーズンまで8年連続でダンロップタイヤ装着チームがコンストラクターズチャンピオンに輝くこととなったのです。
-
1960

ダンロップ社は、濡れたガラス板上を高速で通過できる実験装置をつくり、ハイドロプレーニング現象を初めて解明

乗用車の性能の向上、高速道路網の広がりに伴いタイヤにはより高性能と安全性が求められるようになった。その頃、特に問題になったのはアクアプレーニング、またはハイドロプレーニングと呼ばれる現象である。摩耗したタイヤが少し水のたまった路面を高速で通過すると水の膜の上に浮いた形になり、グリップを失くすことがわかった。このことはダンロップ社の研究所によって明らかにされ、世界中にセンセーションを巻き起こすことになった。研究所では、濡れたガラス板の上を高速で通過できる実験装置をつくり、トレッドの接地状況を撮影して研究を続けた。この研究の結果からトレッドに多数のナイフカットを刻んだタイヤが生まれる。さらにこれに加え、トレッドの外側のリブにアクアジェットと呼ぶ噴水孔のあるトレッドパターンなどが開発された。
-

乗用車用スチールラジアルタイヤ構造図

ラジアルタイヤの普及は、タイヤをより偏平な形に進めた。タイヤの偏平さは、タイヤの断面の高さを幅で割って%で表した数字=偏平率で示される。
初期のタイヤは、高さと幅が同じで、偏平率は100%であったが、その後次第に95%、88%と下がっていった。タイヤを偏平にすると接地面が広がってロードホールディングはよくなり、また横剛性が高くなって安定性も向上する。60年代の終わりには偏平率70%のタイヤが出現し、その後、高性能のクルマには60%、さらに70年代、80年代には偏平率50%以下のタイヤも開発されていった。乗用車用ラジアルタイヤのベルトは70年代の初めからは、全面的にスチールに変わり、また、トラック・バス用にもラジアルタイヤの普及は世界中に進んで、70年代以降はまさにスチールの時代になった。 -

乗用車用ラジアルタイヤの傑作といわれている「ダンロップSPスポーツ」。
1968年のライプチッヒ国際見本市で金賞を受賞。
-
1972

軽いパンクなら所定速度で一定距離の走行が可能なタイヤを開発

ダンロップは1970年になって、ランフラットタイヤの前身となる「DENOVO(デノボ)」を開発します。デノボはホイールにセットしたカートリッジにタイヤ内面が触れると、シーラント剤を噴出して内圧を維持するシステムでした。1972年にはシーラントジェルとリム外れ防止機構を備えた「DENOVO2」へと進化。軽いパンクなら、80km/hで160kmの走行が可能な性能を有していました。
-
1986

岡山県に最新設備を持ったテストコースを建設

20世紀も終盤を迎え、世界的に自動車の高性能化、多様化が進むことになった。こうした動きに対応し、タイヤの開発力を強化し開発スピードを早めるため、1986年、岡山県勝田郡の丘陵に最新設備を持つテストコースが建設された。敷地は約74万平方メートル。自然の道路条件に近づけるため、カーブに傾斜を設けないなど、ヨーロッパやアメリカのグループ各社のテストコースと同じ設計思想を持っていた。ウエット路面での性能評価を行う磨きコンクリート路や滑らかな小石を使った道路、またアメリカのハイウェイにみられるような舗装の継ぎ目や段差のある振動騒音路面などが備えられており、ダンロップの技術開発力をいっそう充実させることになった。
-
1988

空気入りタイヤ実用化100年

1988年はJ.B.ダンロップが空気入りタイヤを発明してから100年目でした。この記念すべき年を前に、日・米・欧に広がる住友ゴムグループはもちろん、直接的な資本関係がない世界のダンロップ社からも、期せずしてこの「空気入りタイヤ1世紀」という機会を捉えてダンロップタイヤの積極的PROMPTを展開してイメージを高めたい、という声が寄せられた。世界でダンロップタイヤを製造している会社は、当社を含め13社を数えた。翌年、オールダンロップの国際広報会議を神戸の当社本社で開催。ダンロップ100年のシンボルマークを作り、積極的にPR活動を展開しました。
フランスのル・マン24時間レースでの国際的なPRでは、名物のダンロップアーチの上に100年のシンボルマークが取り付けられた。この日、ダンロップタイヤを装着したドイツのポルシェ・ワークスが圧倒的な強さを発揮し、8年連続優勝を狙ったが、同じくダンロップタイヤを装着したジャガーチームが31年ぶりに優勝。改めて「強いダンロップ」を印象づけたレースであった。 -
1991
DUNLOP装着のMAZDA787Bで日本車としてル・マン初優勝を飾る
-
1998

最新のハイテクを駆使したシミュレーション技術の「DRS」を発表

ダンロップは高性能なタイヤをよりスピーディに開発する技術として、1998年1月に最新のハイテクを駆使したシミュレーション技術「デジタル・ローリング技術(Digital Rolling Simulation:DRS)」を発表しました。スーパーコンピュータ内で①接地形状/接地圧シミュレーション②摩耗エネルギーシミュレーション③ゴム配合シミュレーション④ノイズ/振動シミュレーションという4つのシミュレーションを見ることを可能とした新技術によって、ダンロップは新世代タイヤの「デジタイヤ」を開発。デジタイヤプロファイル/デジタイヤパターン/デジタイヤシリカ撥水ゴム/デジタイヤカオス配列などを採用したデジタイヤは、その高性能ぶりが市場から高い評価を受けました。
-
現代

CTTプロファイルを採用した第2世代のランフラットタイヤを発表

ダンロップは1970年に「DENOVO」と称するランフラットタイヤの前身を開発し、1979年には進化版の「TDタイヤ」を、1995年にはサイド補強式の第1世代ランフラットタイヤである「DSST」を発表します。そして2000年には、独自のタイヤ形状であるCTTプロファイルを採用した第2世代ランフラットタイヤの「CTTランフラット」を開発しました。サイドの補強層でランフラット性能を、丸いトレッド部で乗り心地などの一般性能を高め、同時に軽量化も施したCTTランフラットは、優れた環境性能と走行性能を実現した先進タイヤとして、大きな注目を集めました。
-

ダンロップ社が開発したパンク時のリムはズレを防ぐデンロックシステムの乗用車用タイヤ断面図

J.B.ダンロップが初めて実用化に成功した空気入りタイヤは、この120余年の間に、その時代、時代の関係者の優れた知識と強い情熱、意志によって着実な進歩を遂げてきた。
現代のタイヤは、20世紀初め頃に比べると、その寿命は数十倍にものびた。ハンドルを切ったときのクルマの動き、走りの安定感、ブレーキのかかり方、乗り心地などは20年前のタイヤに比べても大きく改良されている。パンクの頻度やタイヤの騒音についても同じである。しかし、タイヤの開発に終わりはない。新しい素材の開発が飛躍的にタイヤの性能を向上させることは、これまでの歴史が示している。最近、燃費とグリップの向上を両立させうる新しい合成ゴムも使われるようになった。次々に開発される新素材と、豊富な技術の蓄積を駆使して、さらにロードグリップがよく、ステアリングの性能にすぐれ、安全で乗り心地のよいタイヤを目指し、休むことなく前進し続けることだろう。自動車を路面にのせて走らせる車輪としては、自動車の構造が根本的に変わって空中へ浮くことにでもならない限り、空気入りタイヤがなくなることはないだろう。 -

ポルシェ959用に採用されたDUNLOP DENLOC SP SPORT D40/M2

-
2001

70年ぶりにルマンに挑戦したベントレーが選んだタイヤは再びダンロップ

最高級スポーツセダン・ブランドとして有名なベントレーは、ル・マン24時間レースの初期の時代に、ダンロップ・タイヤを装着して5勝の戦績を残している。2001年には、そのベントレーが70年ぶりにモータースポーツの世界に復帰し、ル・マン24時間レースに挑戦。当時の新型「ベントレー EXP Speed 8」が装着するのは、70年前と同じくダンロップ・タイヤだった。
68回というル・マンの長い歴史において、ダンロップは34勝をあげているが、特に1923年の第一回大会から1930年までの黎明期には、ベントレーとのコンビで、1924、1927、1928、1929、そして1930年に優勝。しかし、残念ながら、ベントレーはその後、モータースポーツから撤退していた。70年ぶりのル・マン挑戦の際に、ベントレーが再びダンロップを選んだことは我々の誇りである。
1周13.6㎞のタフなサーキットを、平均速度200キロ以上で、昼夜にわたって、ドライ、セミウェット、ウェットなど様々なコンディションのなか走り続ける。そのようなハイレベルの走りを支えるために、タイヤに対しても、高度なグリップ、パフォーマンス、そして、耐久性が要求される。ル・マンは、タイヤ・メーカーにとっても究極のチャレンジなのである。 -
2002

『デジタイヤDRSII』が更に進化、氷雪路の路面環境シミュレーションを実現

2002年、ダンロップは独自の技術『デジタイヤDRSII』に氷雪路の路面環境シミュレーションを実現させることに成功。従来の『デジタイヤDRSII』においても、スーパーコンピューターの中でタイヤを車に装着し、実車走行に限りなく近い環境での車の挙動や雨などの路面環境シミュレーションを可能にしていた。それに加えて、新たに氷雪路の路面環境シミュレーションの実現に成功し、1年中スタッドレスタイヤの開発が可能になった。今まで解明されなかった未知の領域に踏み込むことで、厳しい冬道に挑むスタッドレスタイヤの開発において大きな成果を獲得。溝面積を減らしたにも関わらず雪上性能を維持させることに成功した。
-
2005

石油依存度を低減させた新世代エコタイヤ、70%石油外天然資源タイヤ「ENASAVE ES801」を発売

車社会と地球環境の未来のために、限りある石油資源を有効活用し、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の削減に貢献する、新世代の70%石油外天然資源タイヤ「ENASAVE ES801」を2005年に発売。タイヤの原材料に使われる石油系素材「合成ゴム」の使用比率を下げ、ころがり抵抗の少ない「天然ゴム」の使用比率を高めるほか、ゴム補強材、オイル、タイヤ補強材にも天然素材を採用することで、石油外資源比率を一般的なタイヤの44%から70%まで引き上げることに成功した。
-

『デジタイヤDRSII』が更に進化、「タイヤサンド走行シミュレーション」技術を開発

ダンロップはそれまで、精密なタイヤモデルと路面データの組み合わせにより、回転するタイヤのシミュレーションを可能にした「DRS(デジタル・ローリング・シミュレーション)」と、そのシミュレーション領域を拡張した「DRSII」を開発。さらにはゴム材料そのもののシミュレーション技術である「デジコンパウンド」技術を開発し、材料開発から構造開発まで『デジタイヤ』シミュレーションによる一貫したタイヤ開発により大きな成果を挙げてきた。
2005年にはその「DRSII」に「タイヤサンド走行シミュレーション」技術を追加。砂漠や砂浜など砂の上でのタイヤ走行をシミュレーション上で再現することに成功し、これまで中近東等の砂漠で多くの実車テストを要していたサンド走行性能の評価が大幅に効率化。さらにはサンド走行メカニズムの解明によって、スピーディーかつ精密なタイヤ開発が可能になった。 -
2006

耳障りな音を吸い取るサイレントコア(特殊吸音スポンジ)の開発

ダンロップは2006年に世界初の「サイレントコア(特殊吸音スポンジ)」をタイヤ内部に搭載したデジタイヤ「LE MANS LM703」を発売。タイヤが粗い路面を走行する際に発生する車内音(ロードノイズ)の成分の一つに「空洞共鳴音」がある。これは、タイヤが路面の継ぎ目や突起に当たった時、タイヤ空洞内に空気圧の高い部分と低い部分の疎密波が発生して起こる共鳴音で、タイヤ内部の空気の伝播が原因であることから、タイヤの構造や材質による低減対策は困難とされてきた。ダンロップはこの難題に取り組み、新たに開発した「DRSⅢ 空気圧変動シュミレーション」によってタイヤ空洞内の圧力変動を解析し、タイヤ内部にサイレントコアを搭載することにより「空洞共鳴音」を完全に解消することに成功した。
-
2008

97%石油外天然資源タイヤ、「ENASAVE 97」を発売

車社会と地球環境保護のため、石油のみならず石炭などの化石資源への依存度を最小にとどめ、地球温暖化の原因となるCO2の削減に貢献する、石油外天然資源比率97%の新世代エコタイヤ「ENASAVE 97」を2008年3月に発売。すでに2006年には、石油外天然資源比率を70%にまで高めた「ENASAVE ES801」を発売し、各方面から高い評価を獲得。「ENASAVE 97」はこの「ENASAVE ES801」のコンセプトを更に発展させ、新開発のENRテクノロジーの採用により、石油や石炭をはじめとする石油資源への依存度を最小にとどめ、石油外天然資源比率を97%にまで高めることに成功した。当社従来品(EC201)と比較して、転がり抵抗を35%低減し、燃費向上にも貢献。「つくるとき。」「使うとき。」「廃棄するとき。」それぞれの場面でCO2の排出量を削減できる新世代のエコタイヤである。
-
2013

高い静粛性能と優れた操縦安定性能に、低燃費性能を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ「VEURO VE303」を発売

ダンロップは高い静粛性と操縦安定性能に加えて、優れた低燃費性能を実現した新プレミアムコンフォートタイヤの「VEURO VE303」を2013年に発売しました。VE303はハイブリッドバンドを組み込んだ新構造やラグ溝容積を減らした新開発パターン、そしてダンロップ独自のサイレントコア(特殊吸音スポンジ)を採用し、最上級の静粛性能と操縦安定性を確保。さらに、低発熱密着ゴムと新開発パターンの組み合わせにより、転がり抵抗の低減を図るとともにウエットグリップ性能の向上も成し遂げました。
-

100%石油外天然資源タイヤ「エナセーブ100」発売

ダンロップは2011年に「すべての有機物をバイオマス資源に」というコンセプトのもと、原材料のすべてを天然資源化した「100%石油外天然資源タイヤ」のプロトタイプを発表します。その後、量産化技術の確立に向けた取り組みを進め、2013年には100%石油外天然資源タイヤの「エナセーブ 100」を市場に放ちました。石油由来原材料からの天然資源の置き換えは多岐に渡ります。とくに注目したいのが、自然界には存在しない素材をバイオマス技術で創生して石油由来原材料から置き換えし、量産化を実現したこと。とうもろこしや松の木油、菜の花(菜種油)等をバイオマス主原料とし、バイオ老化防止剤やバイオ加硫促進剤、松の木油カーボンブラック、天然ワックス、天然硬化性樹脂などを生み出してタイヤに採用しました。また、ひまし油由来素材の新ジョイントレスバンドや新しいパターンデザインおよびプロファイルなどの導入により、耐摩耗性能の向上も成し遂げました。
-
2014

高精度メタルコア製造システム「NEO-T01」採用のプレミアムランフラットタイヤ「SP SPORT MAXX 050 NEO」を発売

ダンロップが2014年に発売したプレミアムランフラットタイヤの「SP SPORT MAXX 050 NEO」の最大の特長は、“超高精度”を追求した高精度メタルコア製造システム「NEO-T01」を採用した点にあります。快適性能と環境性能、そして安全性能を高次元で実現する最新のタイヤ製造技術のNEO-T01は、①実際の仕上がりのタイヤサイズで創られているタイヤ内側の形状をした金属の成形フォーマー(メタルコア)にタイヤの各種部材を貼り付けていく「メタルコア工法」②部材の生成・加工からメタルコアへの貼り付けまでのすべてを100分の1ミリ単位のコンピュータ制御システムによってコントロールする「全自動連結コントロール」③新たに強靱な素材を補強部材とした「高剛性構造」という3つのキーテクノロジーを用いた工法です。これにより、通常工法のランフラットタイヤと比べて高速ユニフォミティの低減とタイヤ自体の軽量化、そして走行時の形状変化の抑制を成し遂げました。また、新材料開発技術の「4D NANO DESIGN」により創出した新配合ゴムの採用などにより、高次元のウエット性能も実現しました。